地震発生時の備えは大丈夫?:事前確認で安心安全
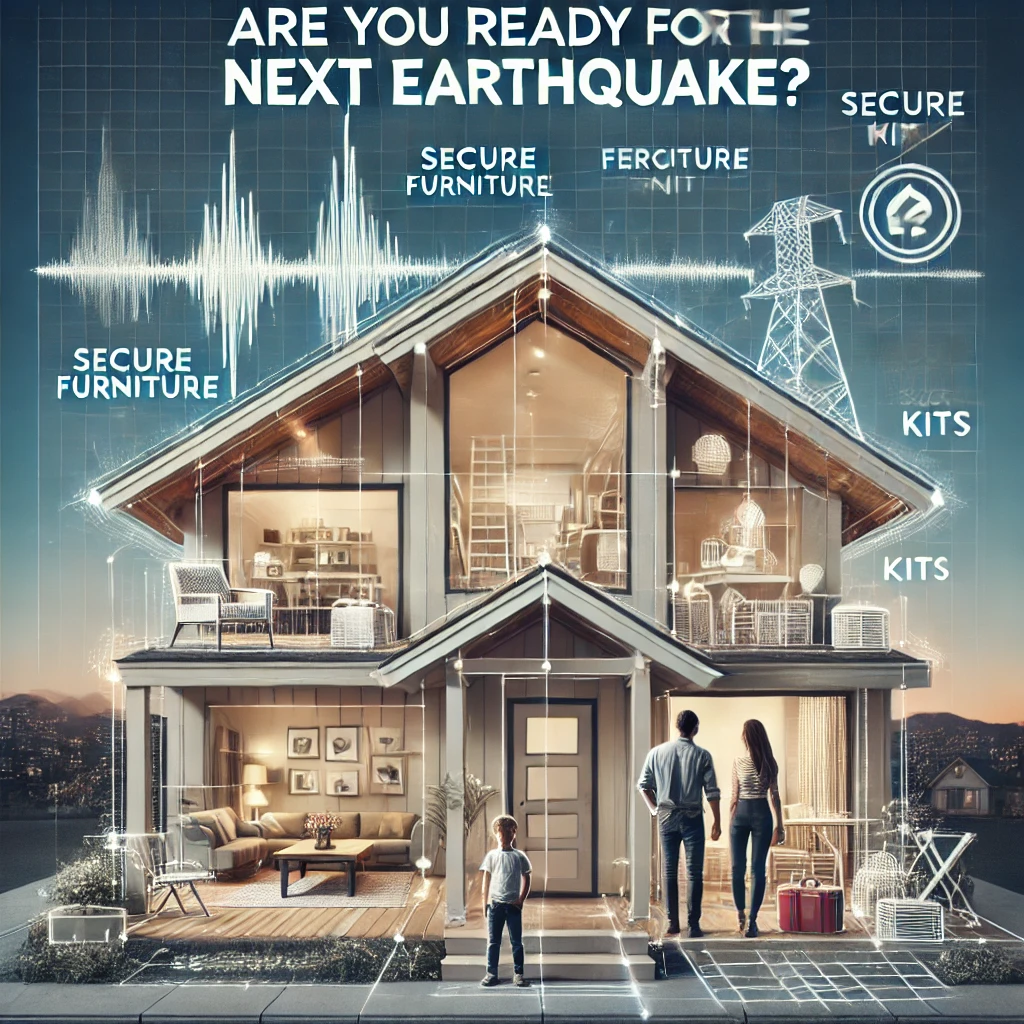
地震対策の基本を知る:安心安全な暮らしのために
地震はいつどこで発生するかわからない自然災害です。特に日本は地震大国と言われ、事前の備えが非常に重要です。万が一の災害時に家族を守り、マイホーム を安全な拠点にするためには、日頃から適切な地震対策を行っておく必要があります。本記事では、地震対策の基本や備えのポイント、さらに具体的な事例を交えてわかりやすく解説します。
地震がもたらす一次災害と二次災害とは?
一次災害とは
一次災害とは、地震そのものによって引き起こされる直接的な被害を指します。建物の倒壊や地割れなどが該当します。
主な一次災害の例:
- 建物の崩壊:耐震性能が不足している住宅に多い。
- 家具の転倒:固定されていない家具が原因。
- 地盤沈下:地震に弱い土地で発生することがある。
二次災害とは
二次災害は、地震によって引き起こされる間接的な被害を指します。火災や津波などが代表的です。また、二次災害は避難所を含めた避難先での発生も含まれます。先の東日本大震災では避難所の環境の悪さによって体調悪化による被害が深刻化しました。
主な二次災害の例:
- 火災:ガス管の破裂や電気系統のショートによる火災。
- 津波:沿岸地域では特に注意が必要。
- 土砂崩れ:地盤が緩んだ山間部で発生する可能性が高い。
- 避難先:急性心筋梗塞などによる死亡事例の発生。基礎疾患の悪化による体調変化が深刻化。
地震対策に必要な準備と注意点
住宅の耐震性能を確認する
耐震等級の確認は、地震対策の第一歩です。住宅性能表示制度に基づく耐震等級は1~3の3段階があります。しかし、現在では性能表示制度よりも高強度の耐震設計である許容応力度計算が普及し始めています。
表1: 耐震等級の基準
| 耐震等級 | 基準 | 特徴 |
|---|---|---|
| 等級1 | 建築基準法を満たす | 最低限の基準 |
| 等級2 | 等級1の1.25倍の耐震性能 | 学校や避難所に採用される基準 |
| 等級3 | 等級1の1.5倍の耐震性能 | 災害時の重要施設(警察署、病院など) |
ポイント: 新築時には最低限耐震等級3を目指す設計をすることで、地震に強い家を実現できます。上記の表示は性能表示といって壁に何を使っているかなどの仕様のみで計算するもので、建物の部材の検討を行わないために簡易的な計算とされています。実際の建物の強度を計算するには『 許容応力度計算 』という構造計算を用いることで、上記の耐震強度よりも信頼性の高い、さらに地震に強い建物を建築できます。建築当初から『 許容応力度計算 』による耐震等級3での設計を依頼しましょう。
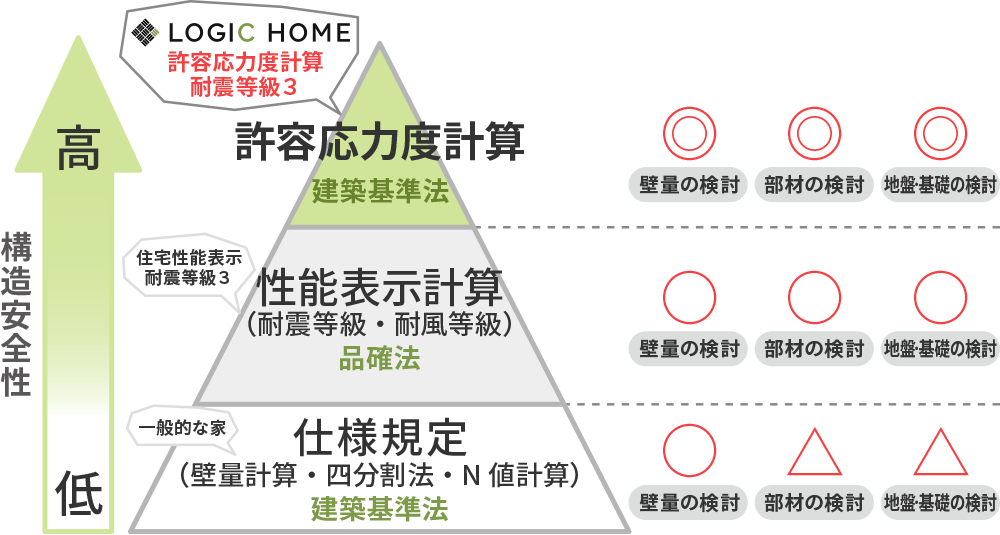
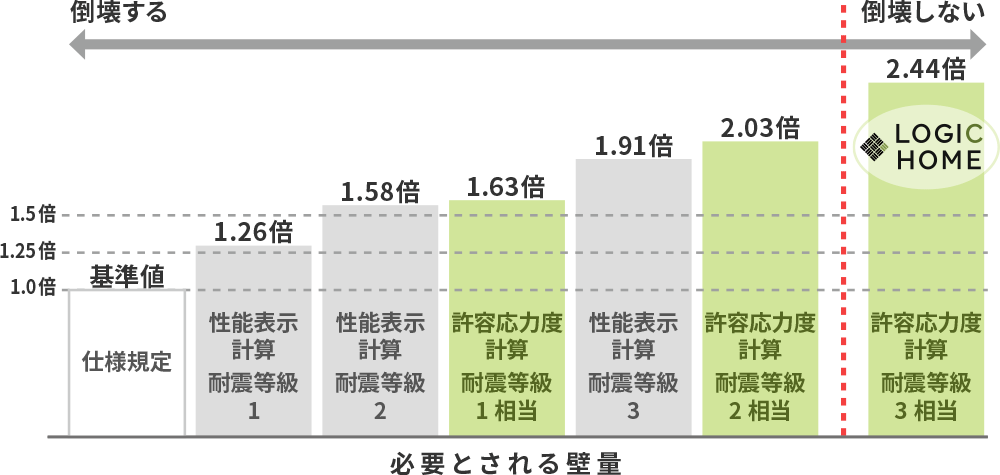
家具や設備の安全対策
住宅内での安全確保のためには、家具や設備の固定が欠かせません。
家具固定のチェックリスト
- 高さのある家具は転倒防止金具で壁に固定する。
- 重い物は家具の下部に配置し、重心を下げる。
- 冷蔵庫やテレビも滑り止めを使用して固定する。
防災グッズの備え
防災グッズを用意することで、被災後の生活を支えることができます。一度地震が発生すると地震の被害が軽微であった被災隣県でも日常品の買い占めが発生するため、日常品が特に不足します。女性用品が特に先の震災では不足する傾向が見られ、とても大きな不便が発生したようです。日常的に使用しているもの特に使用期限がないものは多めにストックすることが必要です。
防災グッズの例
| アイテム | 用途 | 備考 |
|---|---|---|
| 非常食・飲料水 | 食糧と水の確保 | 家族全員分を最低3日分用意する |
| モバイルバッテリー | 通信手段を確保 | スマホやライトの充電に必要 |
| 防災ラジオ | 情報収集 | 電池式や手回し式が便利 |
| 簡易トイレ | 衛生管理 | 断水時の備え |
実際の事例から学ぶ地震対策の重要性
事例1:家具の転倒によるけがを防いだ家族
福井県あわら市在住のAさんは、2024年年始の能登半島地震前にすべての家具を壁に固定する対策を行っていました。地震発生時震度5に遭遇しましたが、家族全員が無事だったのは、転倒防止金具が効果を発揮したおかげです。
ポイント: 家具固定は簡単な作業ですが、大きな効果をもたらします。ご高齢のご家族のみで施工が難しい場合は近隣のご家庭にお願いするなどで確実な対策を行いましょう。地域の区長さんに相談すると良い方法を教えてもらえたり、お手伝いの手配などが望めます。
事例2:耐震等級3の家で被害を最小限に
2021年の地震で、耐震等級3の家に住むBさん一家はほぼ被害を受けませんでした。この建物には耐震等級3に合わせて制振装置が設置されていたようです。一方、近隣の耐震性能が低い家では、屋根瓦の落下や壁のひび割れが多数発生し住宅の補修には順番待ちが発生し、補修完了までに1年かかったそうです。
教訓: 耐震性能は新築時にしっかり確認することが重要です。むしろ新築時でしか対応できない項目です。後からの回収では構造計算もできないため、勘に近い耐震改修しかできません。
地震対策を進める手順
ステップ1:住宅の耐震診断を行う
既存の住宅に住む場合、耐震診断を受けることをおすすめします。診断結果に基づき、補強工事やリフォームを検討しましょう。新築時の耐震設計までの強度補強は望めませんが、それでも対策することは確実に地震対策となります。中古住宅を購入する場合は、シロアリの自分での調査(業者任せには絶対にしないこと!)が必要です。命は何よりも大事です。昭和56年以前の建物は新耐震基準ではないために地震に対する性能は皆無だと思ってください。新耐震基準が義務化されたのは2000年以降です。昭和56年以降だとしても安心とは限りません。
ステップ2:日常的な防災意識を高める
日頃から避難経路の確認や防災訓練に参加することで、地震への対応力を養うことができます。
まとめ:事前の備えが安心安全をもたらす
地震は避けられない災害ですが、事前の備え次第で被害を大幅に軽減することができます。以下のポイントを実践し、安心安全な暮らし を実現しましょう:
- 新築時には『 許容応力度計算の耐震等級3 』の住宅を選ぶ。
- 制振装置を必ず採用し、新築当初の耐震性能を維持する。
- 家具固定や防災グッズの準備を徹底する。
- 日常的に防災意識を高め避難先の確認、万が一の場合の集合場所の確認。
今すぐできることから始めて、家族全員で災害に備えましょう。いつか起こるだろうではなく、いつか必ず起きるという考え方に変えましょう。

