注文住宅での失敗を避けるための10のポイント
注文住宅は、家族のライフスタイルやこだわりを反映させる夢の住まいを実現する一方で、事前にしっかり計画を立てないと後悔を生む結果にもなりかねません。この記事では、注文住宅での失敗を避けるための10のポイントを解説し、あなたの理想のマイホームづくりをサポートします。新築一戸建て マイホーム 注文住宅 の計画を進める前にぜひ参考にしてください。
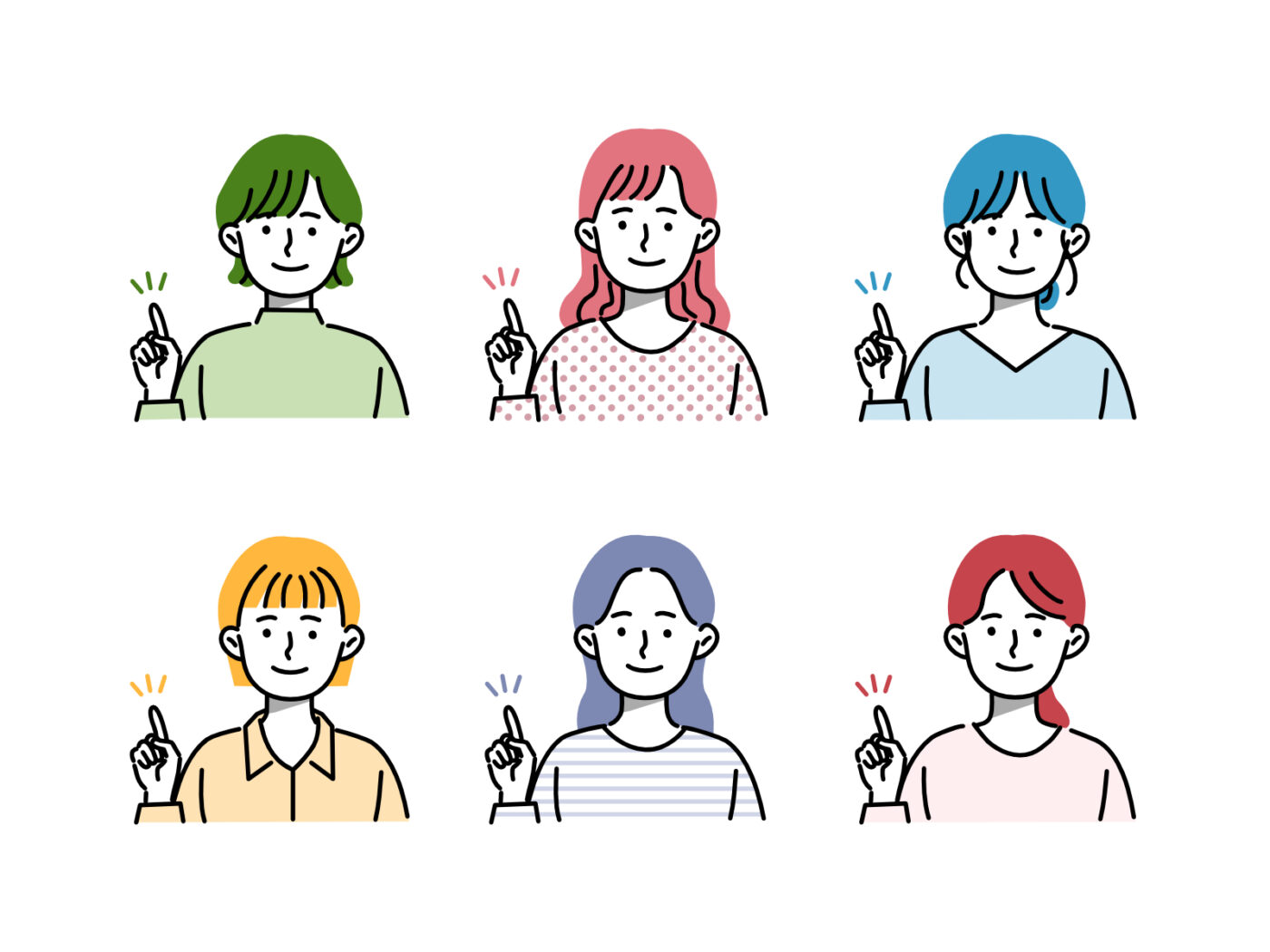
ポイント1: 自分たちのライフスタイルを明確にする
家づくりの第一歩は、自分たちのライフスタイルをしっかり把握することです。家族の構成や生活パターン、仕事の形態、趣味などを考慮し、今後のライフスタイルに適した間取りや設備を考えましょう。
具体例: テレワークのスペース確保
最近ではテレワークの普及が進み、仕事に集中できるスペースを設けることが重要です。お家時間を楽しむ、テレワークを快適にするためには、静かな場所にホームオフィスを設置するなど、ライフスタイルに合った設計を心がけましょう。家族との触れ合いを重視する場合、それぞれのプライベートを重視する場合などライフスタイルによって、間取りや、インテリア、デザインが大きく異なります。
失敗例
日常の家事や子育ての動線を考えずに間取りを決めてしまい、結果として不便な生活動線が生じてしまうケースがあります。日常の行動パターンを把握し、必要な動線を確保することが大切です。
ポイント2: 十分な予算計画を立てる
予算計画は家づくりの最も重要な要素の一つです。家の価格だけでなく、家具や家電、外構費用、さらには税金や諸費用も考慮に入れて計画を立てる必要があります。特に建物のグレードによって、仕様や性能が大きく変わるため、生涯コストが全く違います。生涯コストは家と同じくらいの差を、建物のグレードによって発生することが多く、ほとんどの場合住宅会社からのこの点についての説明はありません。ステルスキラーと言われる部分です。しっかりとこの生涯コストに注目することで満足度の高い家づくりを行うことができます。
具体例: 予算の配分
例えば、インテリアや暮らしにこだわりたい場合、家具やデザインのコストを事前に見積もっておくことが重要です。オシャレな家を実現するためには、見た目と実用性を両立させる予算配分を考慮しましょう。
失敗例
当初の予算を超えてしまい、必要な部分で妥協を迫られるケースがよくあります。予算オーバーを防ぐために、余裕を持った計画が必要です。また、最初には気づかない生涯コストを建築後に気づいたことで、家づくりを後悔する方が多く見られます。デザインばかりを気にしてしまい、生涯で大きなお金を支払うことになってしまいます。子供の教育資金に等しいほどのコストの差が開くことを最初に知っていれば、妥協のない家づくりを行えたかもしれません。
ポイント3: 保証の内容をしっかりと確認する
家づくりは保証内容によって万が一の際の対応が変わります。特にトラブルになりやすいポイントは設備の不具合などの対応です。住宅で使用されている設備は多岐にわたるため、故障やトラブルの際には大きな負担を伴います。特に電化製品である、IHヒーターやエコキュートなどの電化製品は電化製品と言われるだけあって、当たり外れもあり、故障などのトラブルがつきものです。大概の場合、メーカーの初期保証が1〜2年程度ついていますが、それ以降の保証はありません。つまりは故障などで修理や入れ替えが発生した場合は、施主負担となります。エコキュートなどは6〜8年で壊れることが多く、入れ替えとなれば45万円ほどの費用が発生します。長い保証があればこのような大きな負担を削減することができます。備えあれば憂いなしと言いますが、保証は万が一のお守りなのです。
具体例: エコキュートがまさかの5年後に故障
運が悪く新築5年後にエコキュートが故障。この時は基盤の故障のみのため長期補償によって基盤交換で対応できました。しかし、その2年後に今度は完全に壊れてしまいました。この時も長期保証があったことで無償で同等品の新品に交換することができました。もし、設備機器保証がなかったら基盤交換の3万円と新品交換費で45万円ほどの出費となっていました。
失敗例
設備機器保証が保証内容に組み込まれていなかった住宅会社で建築した為、7年後にエコキュートの交換費45万円を支払うことになりました。運が悪くエコキュートのみならず、高価な換気システムも故障が発生し、この時に修理費用で20万円が発生しました。設備機器保証があればこの負担は防げたことでしょう。保証範囲外のため、施工会社は相手にしてくれず、全額お客様の負担となってしまいました。
ポイント4: 将来のライフプランを考慮する
注文住宅を建てる際には、現在のライフスタイルだけでなく、将来の家族構成や年齢を考慮して設計を行うことが大切です。将来的な二世帯住宅や老後の暮らしを見据えた設計が後悔を防ぎます。
具体例: バリアフリー設計
例えば、老後を見据えてバリアフリーに対応できる設計や、平屋を選択することで、長く快適に暮らせる家づくりが実現します。また、家事楽を意識した間取りや設備選びも重要です。最近では寝室を1階に設計士、2階は子供の部屋のみにする半平屋住宅も増えてきています。
失敗例
子供が大きくなった際に部屋が足りなくなる、もしくは逆に子供が独立して使わない部屋が増えるなど、将来の変化に対応できない間取りは避けましょう。
ポイント5: 間取りに無駄を作らない
間取りは、家づくりの基本です。部屋の数や配置、廊下の使い方などを慎重に検討し、無駄のない空間を設計することが大切です。広すぎる廊下や無駄なスペースはコストアップにつながります。プレミアムコンパクトの考え方が主流の昨今では、高性能住宅をコンパクトに建てることで、生涯コストを削減するとともに快適な住環境を実現することができます。
具体例: 開放的なリビング
リビングを広めに設計し、開放感のある空間を作ることで、家族のコミュニケーションが増えます。カフェ風のインテリアを取り入れたデザインも人気です。
失敗例
収納スペースを十分に確保しなかったり、家事動線を考慮しなかった結果、日常生活で不便さを感じることがあります。収納や動線も重要な設計要素です。
ポイント6: エネルギー効率を考える
エネルギー効率の良い家は、長期的なコスト削減につながります。断熱性能や太陽光発電システムの導入を検討し、環境に優しい家づくりを目指しましょう。
具体例: 断熱等級7の家づくり
近年注目されているのが、断熱等級7の家づくりです。国が定めた断熱性能を示す性能値を等級で示しています。最高ランクである断熱等級7の家は圧倒的な省エネ住宅です。断熱等級5・6と7では建物の快適性能に大きな差が開き、一生住み続ける住宅では、上昇し続ける電気代で相当大きな差が開きます。妥協のない断熱性能を実現することで一生快適な住環境で住み続けることができます。特に老後は収入も減り、在宅率が増えるため大きな差を生み出します。
失敗例
断熱性能が低い家は、冬場の光熱費が高騰することがあります。最初のコストは高めですが、長期的な省エネ効果を見込んで投資することが重要です。最近では電気料金の高騰から断熱性能の低い家では電気代が大きく負担となっています。後悔しないためには断熱性能は妥協できません。
ポイント7: 耐震性能を重視する
耐震性能は日本の住宅において欠かせない要素です。特に地震の多い地域では、最新の耐震技術を導入することが安心安全な住まいを作るためのポイントです。最高の耐震性能と、制振装置の採用で安心安全な家づくりをお勧めします。
具体例: 耐震等級の確認
建築基準法で定められた耐震等級の中でも、耐震等級3は最も高い耐震性能を誇ります。その中でも許容応力度計算の耐震等級3をしっかり確保することで、大地震時でも安全に過ごせる住まいを提供できます。
失敗例
耐震性能を軽視し、建物が地震によって大きな損害を受けるリスクを負うケースがあります。初期投資を惜しまず、耐震対策をしっかり施しましょう。後悔先に立たずです。
ポイント8: 家事を楽にする設備を導入する
家事負担を軽減するための設備や間取りを考慮することで、日々の生活がより快適になります。家事動線や収納の配置も重要な要素です。
具体例: 家事楽アイテムの導入
家事を楽にする設備として、食洗機やランドリールーム、家事動線を考えた間取りが注目されています。例えば、キッチンとランドリールームを近くに配置することで、効率的に家事がこなせます。家事と子育ての時間帯は被ることが多いため、奥様の家事負担を削減するには、家事楽設備や、家事動線の短さは必須の検討ポイントです。
失敗例
家事動線が悪いと、家事にかかる時間や労力が増えてしまいます。特に収納や家事スペースを計画的に配置することが大切です。
ポイント9: モデルハウスを参考にする
モデルハウスを参考にすることで、自分たちのイメージに合った家づくりが可能になります。施工業者のホームページやモデルハウスを活用して、理想の住宅像を明確にしましょう。多くの住宅会社が出店している総合展示場では、各社オプションの館と言われるほどオプションだらけのモデルハウスが展示されています。このイメージのまま家づくりを行うと、自宅が完成した際のイメージと大きく乖離してしまい、適正な価格だったのかが建ててから大きな後悔を生んでしまいます。現実的なモデルハウスを確認し、その建物がいくらで建てられるのかをしっかりと確認することが大切です。
具体例: 施工事例の活用
カフェ風デザインや平屋、リノベーション事例など、さまざまな施工事例を参考にすることで、自分たちの理想に近い設計が見つかります。
失敗例
理想のイメージを持たずに家づくりを進めると、完成後に後悔することがあります。施工事例をしっかり確認し、自分たちの好みに合ったデザインを見つけましょう。
ポイント10: 設計士とのコミュニケーションを大切にする
最後に重要なのは、設計士とのコミュニケーションです。家づくりにおいて、設計者との意見交換は不可欠です。疑問点や要望をしっかり伝えることで、失敗を防ぎます。最近ではコスト削減のために、無資格の営業マンがプランが書くことが散見されますが、設計士の資格を持ったプロの設計士にしっかりと要望を伝え、性能に欠陥が出ないようなプランを作成してもらいましょう。
具体例: 意見交換の大切さ
設計士と定期的にミーティングを行い、自分たちの希望や疑問点を明確に伝えることが、理想の家づくりに繋がります。自由設計を最大限活用しましょう。
失敗例
設計士と十分なコミュニケーションを取らずに進行すると、完成した家が自分たちのイメージと違うと感じることがあります。常に情報共有を大切にしてください。
まとめ
注文住宅での失敗を避けるための10のポイントを理解しておけば、理想のマイホームを作るための基盤が整います。暮らしを楽しむためには、自分たちのライフスタイルに合わせた設計や設備の導入、予算計画、そして施工業者との信頼関係が不可欠です。長く快適に過ごせる家づくりのために、これらのポイントをしっかり押さえて進めていきましょう。

